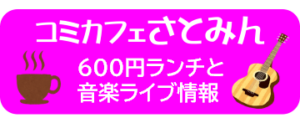札幌市清田区里塚1条1丁目、2丁目地区で起きた大きな地震被害は、地下の土が液状化して地滑りを起こし、大量の土が流失。その結果、地下が空洞化して地盤沈下や家屋の傾き、倒壊が起きたのではないかと見られています。
この地区は、昭和53年、54年ごろ谷状の地形を盛り土して宅地造成されたといいます。
もともとは、どんな地形だったのでしょうか。
ここに宅地造成する前の旧地形図があります。昭和40年(1965年)札幌市現況図(2500分の1)(旧地形図)です。湾曲しているのが旧道です。旧道の形は今と変わりありません。

昭和40年札幌市現況図(旧地形図)の里塚1条1丁目、2丁目付近
被害が大きかったこの地区(旧道の左下の地域)は現在、緩やかな傾斜があるものの比較的平たんな住宅地になっています。
ところが、宅地造成前の地形は、谷と山が幾重か続く地形でした。等高線の間隔も狭く急な山と谷の地形だったことがうかがわれます。旧地形図の①の部分はかつての谷筋で、今回、最も大きな被害が発生した地域と見られます。
宅地造成される前、標高は50m~60mほどの谷底平野だったことが旧地形図から読み取れます。水田として利用されていました。近くの山の部分は標高80m超の高さがあり、谷の部分とは20~30mほどの高低差があったことがうかがわれます。

国土地理院の現在の地図
このあたりは、山を切り土して、谷を盛り土して宅地造成したと言われています。国土地理院の地図によると、この辺りは現在、標高が概ね55m~65mほどの宅地になっています。
上の旧地形図①の谷には、水田沿いに2本の川があったと、札幌市宅地課は説明しています。川は三里川の本流と支流とみられます。本流は、宅地造成の際、暗渠(あんきょ、地下水路)になりましたが、支流はどうなったのでしょうか。地下の水の流れが気になります。
旧地形図②の谷筋は、畑だったようです。国土地理院の「札幌市清田区の地形復元図」によると、旧地形図②の谷筋は「谷底平野」でした。ということは、ここも川か沢があったと思われます。

清田区地形復元図(国土地理院)青い部分が、かつての「谷底平野」。緑は「山地・斜面」、茶色は「台地」、ピンクがかった水色は「台地(定位段丘面)」
しかし、札幌市作成の河川網図によると、この川ないし沢は暗渠になっていません。盛り土した後、かつての水の流れはどこへ行ったのでしょうか。これも気になります。

暗渠化された三里川。緑色の線が暗渠(札幌市河川網図)
旧地形図③の谷筋は、水田や畑だったようです。現在、この先の延長線上に市営住宅里塚団地があり、地下に暗渠「三里東排水」が走っています。暗渠「三里東排水」は美しが丘の住宅街を通って里塚霊園まで続いています。

液状化が起きた美しが丘3条6丁目
このラインでも今回、美しが丘地区で液状化や地盤沈下、家の傾きなどの被害が発生しています(美しが丘3条6丁目など)。この地区は2003年の十勝沖地震の時も液状化や家の傾きが起きています。
市営住宅里塚団地は、窪地に集合住宅が建ち並んでいます。なぜ窪地なのでしょうか。ここは、かつて旧地形図③の谷筋でした。ここは盛り土しなかったのかもしれません。
ところで、札幌市の大規模盛土造成地マップ(盛り土マップ、2017年公開)に今回、大きな被害が発生した里塚地域は掲載されていません。
今回ここで紹介した昭和40年の札幌市現況図(旧地形図)は、まさに札幌市が盛土マップを作製した際に基準とした地形図でした。

緑色が盛土部分。国道36号を越えて、その先の上の部分が今回の被害地域。盛り土であることが記載されていない。
札幌市宅地化によると、昭和40年の旧地形図と現地形図の高低差が3m以上あるところをコンピュータで抽出し、そのうえで小規模の盛り土地区を除外するなどして作成したそうです。しかし、昭和40年当時の旧地形図は等高線が5m間隔と粗く、判読不明な等高線もあり、コンピュータの集計から漏れてしまったそうです。
今回の地震後、札幌市は、里塚の被害地区が盛り土でできた宅地であることを認めています。
[広告]