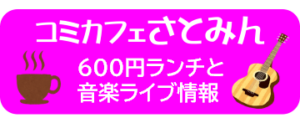今年の夏は町内会の夏祭り・盆踊りが軒並み中止です。コロナの感染は収束の気配がなく、9月以降も清田区内の主な地域イベントは相次いで中止が決まっています。コロナ禍で経済活動への甚大な影響が問題になっていますが、地域の活動も止まったままで問題です。

注目される全自動PCR検査機
感染を抑止するために自粛を強めたら社会経済活動が止まってしまう。経済や社会を回すために自粛を緩めたら感染が増えてしまう。困ったものです。
ところが、ここにきて、感染を抑止しながら社会経済活動を動かす方法として、PCR検査の拡充が注目されてきているようです。
PCR検査を増やして、感染者とりわけ無症状の感染者をなるべく多く発見して隔離・療養し、社会から感染リスクを小さくして社会経済活動を動かすという考え方です。東京都世田谷区や長崎県、東京都医師会が、こうした方針を打ち出しています。

夏祭りのない夏
清田区では多くの町内会が、夏祭りや親睦バスツアー、夏休みラジオ体操、子供会活動などの行事を中止しています。地域のつながりをつくる大事な活動ですが、今春以降、それができない状態が続いています。
高齢者を見守る福まち活動や、子供たちの健全育成を図る青少年育成委員会の諸活動、老人クラブの活動なども、思うように活動ができない状態が続いています。
9月以降も厚別(あしりべつ)神社のお祭りをはじめ、平岡樹芸センターの庭園コンサート、白旗山スポーツフェスタ、清田区民文化祭など軒並み地域のイベントは中止が決まっています。しかも、こうした地域イベントが、この先、再開できる見通しもまったく立っていないのが実情です。
地域の活動が再開できない大きな原因は「人が集まると、感染するのでは」という不安があるからです。
しかも町内会をはじめ地域の活動は年配者、高齢者が中心になって担っているケースが多く、「コロナは高齢者ほど重症化する」ともいわれているだけに、感染への不安から再開できないでいるのです。「マスクと消毒と三密回避」という対策だけでは、不安は払拭できないのです。
コロナは無症状の感染者からも感染するといわれています。無症状の感染者がどこにいるかも分からない社会では、とりわけ年配者や高齢者は不安で活動を再開する気持ちになれません。
この「不安」をかなり小さくすることができれば、少しは地域活動が再開できるかもしれません。そのカギとして最近、指摘されているのがPCR検査の拡充です。検査を可能な限り増やし、陽性者は隔離・療養とし、「感染するのでは」という不安を極力少なくして経済や社会を回すという発想です。
先日、報道された日本の検査数の少なさに驚きましたが、それを克服しようとする動きも少しずつ出てきたようです。
■日本のPCR検査数 世界の159位
世界のコロナ関連の統計を扱っている米ウェブサイト「worldometer」によると、人口当たりのPCR検査実施数は、日本は世界215の国・地域の中で159位だそうです(7月28日時点)。最貧国並みの衝撃の数字です。
もっと増やせないものでしょうか。日本は検査数が圧倒的に少ないので、無症状の感染者が市中のあちこちにいるのではないか、という不安が消えません。
■世田谷モデル
東京都世田谷区は現在、1日200~300件のPCR検査数を当面、1日600件に拡充し、さらに1日2000~3000件の検査を目指す方針を打ち出しました。最終的には、感染を抑止したニューヨークのように「いつでも、どこでも、何度でも」ということを目指すべきとしています。
検査数を増やすために、コストを下げ労力も省ける「全自動PCR検査機」を導入し、複数の検体をまとめて検査する「プール方式」を採用する考えです。プール方式とは、複数の検体を混ぜて検査し、陽性反応が出た場合だけ1人ずつ検査するやり方で、検査効率が高まり、件数を増やせるといいます。
当面は、医療や介護、学校、保育などの従事者(エッセンシャルワーカー)を中心に検査を拡充するとしています。いずれ無症状者にも検査を拡充する方針です。
検査拡大のシステムは、深刻な感染拡大が起きた米国ニューヨークが既に実施し、感染拡大抑止という成果を挙げている方法です。世田谷モデルはニューヨークのやり方に学んだ方法という訳です。
世田谷区の保坂展人区長は「最大の経済対策は、いつでも、どこでも、何度でもPCR検査をできる体制づくりだ」と言っています。PCR検査施設は医療施設ではありますが、見方を変えれば、経済インフラでもあるように思えます。
しかし、課題もありそうです。予算をどう工面するのか、感染者の受け入れ態勢をどうするのか、人員は確保できるのか等々、簡単ではない問題もありそうです。課題を乗り越えて、いい先進例を見せてほしいものです。
■東京都医師会の決断
東京都医師会は、PCR検査が受けられる医療機関を都内で1400カ所(人口1万人に1カ所)まで増やす検討を始めています。先日、東京都医師会長が記者会見して発表しました。「感染者を早期に見つける体制を地域で確立する必要がある」という考えです。
「人口1万人に1カ所」を札幌市に当てはめると197カ所、清田区に当てはめると11カ所の検査施設開設となります。
■長崎モデル
長崎県医師会と長崎大学、長崎大学病院は8月3日、無症状でも希望すれば地域のかかりつけ医などでPCR検査を受けられる体制を整備したと発表しました。8月中旬から長崎市などから始め、全県、離島に拡大していくといいます。
長崎県医師会は、保健所を管轄する県、長崎市、佐世保市と委託検査の集合契約を結び、医師会所属の医師のいる医療機関で、唾液を採取して長崎大学病院に搬送し、検査するといいます。
■小林慶一郎氏の提言
東京財団政策研究所研究主幹で、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会のメンバーを務める小林慶一郎氏は、メディアで頻繁に「検査と隔離」の重要性を説いています。
「感染のリスクが高いと、経済が回りません。間違いなく萎縮してしまいます。消費者が怖がって旅行に行かなくなったり、外出しなくなったりするのは当然のことです。どうすればリスクを下げられるかを考えると、検査をして陽性者を隔離するしかありません」(AERA)。
厚生労働省が8月7日発表したところによると、全国のPCR検査能力は1日5万2000件です。国も検査能力を増やしてきています。小林氏はこれを1日20万件まで早急に拡充することを提案しています。
小林氏は経済のことを念頭に提案していますが、これは地域の活動にも言えることだと思います。感染リスクが高いと、地域の活動も止まってしまうからです。
厚生労働省によると、北海道内のPCR検査能力は1日1800件だそうです。
札幌市も、秋元市長が北海道新聞のインタビューで「PCR検査を増やす」と述べています(北海道新聞8月5日)。PCR検査を拡充して、市民の不安を解消してほしいです。そうすれば経済も地域社会も今よりは動くと思います。
[広告]