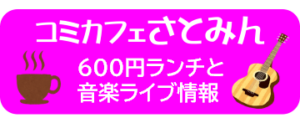札幌国際大学の学生40名余が5月9日(金)と13日(火)の2回、あしりべつ郷土館の協力で清田区の歴史を学び、北野に残る歴史遺産「吉田用水」跡を探訪しました。

吉田用水跡で了寛氏から説明を受ける札幌国際大学の学生たち=北野3条3丁目
これは同大学の平塚彰教授の授業の一環で、今年で4年目となります。講師は、あしりべつ郷土館運営企画委員の了寛紀明氏(郷土史家)と川島亨氏(「ひろまある清田」代表)が務めました。
5月9日は、清田区民センターで了寛氏から、清田区150年の歴史を学びました。

清田150年の歴史を学ぶ
了寛氏は、清田区の昔の地名「厚別(あしりべつ)」の語源や、明治6年(1873年)に清田区を貫く札幌本道(函館―札幌、国道36号線のルーツ)が出来たこと、同年、札幌本道(現旧道)の清田小学校付近に休泊所が置かれ、人々の行き来が始まったことなどを紹介。

あしりべつ郷土館内を見学
さらに、明治の開拓期、平岡や真栄、有明には山鼻屯田、新琴似屯田、篠路屯田などの広大な公有地や給与地があったこと、清田は長らく農村地帯だったけど昭和40年代頃から急速に宅地化がすすみ、札幌市内の閑静な住宅地区に変貌し発展してきたことなどを紹介しました。
そのほか、学生たちは清田区民センター2階のあしりべつ郷土館で、清田区の先人が使っていた生活道具や農機具などを見学しました。
5月13日(火)は、明治25年(1892年)頃に造成された農業用水路「吉田用水」の記念碑と吉田用水跡を現地に行き、見学しました。

吉田用水記念碑を見学=厚別川左岸道路脇
吉田用水は今のコカ・コーラ裏手の厚別(あしりべつ)川左岸から取水し、北野、大谷地、流通センター方面に水田用水を供給した最初の大型用水路。長さは約5㎞に及びましたが、昭和40年代に地域の宅地化と共に水田が消え、役目を終えました。ただし、今でも北野3条3丁目に長さ500mの帯状の緑地帯として、その痕跡が残っています。

八重桜が咲く吉田用水路跡を歩く学生たち
学生たちは、初めにコカ・コーラ裏手(厚別川左岸道路脇)に建つ「吉田用水記念碑」を見学。それから歩いて北野3条3丁目の吉田用水跡に行きました。

用水路跡の終点
吉田用水という名称は、この用水路造成に尽力した吉田善太郎という当時の地元有力者の名前から付けられたものです。学生たちは吉田用水路跡を歩きながら、吉田善太郎の足跡についても、様々な話を学びました。
吉田用水の造成により水田が100ヘクタールも増えたといいます。吉田用水は、この地域を稲作地帯として発展させる大きな契機となりました。
[広告]