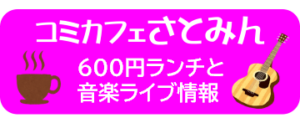北海道里程元標前で=創成橋たもと
清田区民センターとあしりべつ郷土館は6月21日(土)、札幌中心部から島松まで、かつての札幌本道(現国道36号線のルーツ)の「里程標」(明治期に建てられていた1里=4㎞ごとの標識)をめぐる歴史探訪バスツアーを実施しました。

「一里標跡」の説明板前で=豊平区月寒西1条2丁目
札幌本道とは、開拓使が明治6年(1873年)に開削した函館から札幌(森―室蘭間は海路)までの北海道最初の幹線道路(馬車道)で、清田区内は今の「旧道」(北野―里塚)に当たります。

建て替えられた二里標があった場所=北海道農業研究センター入り口付近
札幌本道のうち札幌―室蘭間は「室蘭街道」とも呼ばれ、国道36号のルーツです。
開拓使は、創成川に架かる創成橋(札幌市中央区南1条東1丁目)のたもとに北海道里程元標を建て、そこを基準に1里ごとに里程標を建てました(明治6年)。今はありません。

開拓使の「新道出来形絵図」に描かれた札幌本道と三里川(明治6年)。川のほとりに「従札幌第3号」と書かれた三里標が建っている
三里標(三里塚)は、清田区里塚2条2丁目の三里川ほとりに建てられ、このことから川の名を「三里川」、地名を「三里塚」と呼ぶようになりました。地名は昭和19年(1944年)に「三」を取って、今の「里塚」になり、今日に至っています。

明治6年の二里標があった付近=つきさむ温泉付近
今回の歴史探訪バスツアーは、北海道里程元票(今は役目を終え、モニュメントが建っています)から、一里塚(月寒)、二里塚(月寒東)、三里塚(里塚)、四里塚(大曲)、五里塚(輪厚)、6里塚(島松)を辿る郷土史探訪ツアーです。
約50人が参加。大型バスに乗り、清田区民センターを出発し、まず北海道里程元標に向かいました。
ガイドは、あしりべつ郷土館企画運営委員の了寛紀明さん(郷土史研究家)と同じく川島亨さん(「ひろまある清田」代表)、そして清田区民センター運営委員の杉本雅章さんの3人が務めました。

駐輦之所碑(明治14年、明治天皇が行幸の途中、休憩した場所)=豊平区月寒東1条19丁目
バスの車中や、里程標があった付近などで降車しては、了寛さんらから付近の歴史エピソードなど興味深い話を聴きました。
今回のバスツアーでは、各里程標に以下のような大きな歴史ミステリーが存在することが紹介されました。
各里程標は明治6年に建てられた後、建て替えられたことが分かっています。しかも不思議なことに、各里程標はすべて明治6年建立の里程標よりも800m~1㎞も札幌寄りに建っていました。

建て替えられた三里標があった場所=清田区平岡2条4丁目
建て替えられた三里標は、なんと平岡2条4丁目の旧道沿いに建っていました。明治6年の三里標よりかなり札幌寄りです。これは目撃証言が残されています。建て替えられた三里標も昭和20年代にはなくなったといいます。
建て替えがいつ行われたのか、なぜ建て替えられたのか、なぜ札幌寄りだったのか、分かっておらず歴史ミステリーになっています。
明治14年(1881年)に明治天皇御巡幸の際に建て替えられたとの説もありますが、了寛さんは疑問符を投げかけています。明治6年の里程標も、後年に建て替えられた里程標も、現存するものは一つもありません。

平岡南公園の旧道沿いに建つ三里塚碑。しかし、ここには三里標(三里塚)はなかった
今回の札幌本道バスツアーでは、明治6年の里程標と建て替えられた里程標の両方を訪ね、その都度参加者はバスを降り、了寛紀明さんらの解説に耳を傾けました。

明治6年の三里標があった三里川のたもと付近=清田区里塚2条2丁目
清田区の平岡南公園(清田区平岡2条6丁目)の旧道沿いに「三里塚」碑が立っています。これは、2004年に建立されたものですが、ここは三里標が建っていた場所ではありません。関係ない所に建っているのです。
札幌市内や近郊の郷土史家の中には「三里塚は平岡南公園の所にあった」などと誤解しネットなどで発表することが多く、弊害が生じています。三里川のほとりに移すべきでしょう。

ツアーの終点、島松(六里標)付近を歩く
朝から夕方まで一日かけた歴史探訪バスツアーでしたが、参加者は「とても面白いツアーでした」「知らなかったことが多く、興味深かった」など感想を述べていました。清田区外からの参加者も結構いました。

「札幌本道 歴史探訪バスツアー」の行程図(茶色の線)
[広告]