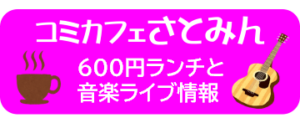平岡公園梅林で5月1日(水祝)、梅の花の解説を聞きながら梅林を見て歩く梅林ツアーが行われました。約20人の市民が参加し、ウメの花のあれこれを学びました。
平岡公園管理事務所が開催したイベントで、公園職員がガイドしました。
平岡公園には6.5ヘクタールの梅林に約1200本の梅の木が植栽されています。紅梅と白梅は4:6の比率だそうです。
この日は、「白梅が1分咲き、紅梅は未開花」という発表でしたが、これは基準木で判定したものです。実際は、結構、花が咲いている紅梅もありました。
 梅林ツアーでは、ウメの歴史や平岡公園のウメの木の管理の苦労、白梅と紅梅の違いなど興味深い話を聞きながら、約1時間かけて梅林を歩いて回りました。
梅林ツアーでは、ウメの歴史や平岡公園のウメの木の管理の苦労、白梅と紅梅の違いなど興味深い話を聞きながら、約1時間かけて梅林を歩いて回りました。
平岡公園のウメは、もともとここにあったものではありません。公園は昭和57年から造成され、ウメはすべて移植されたものです。
当時、札幌市は百合が原公園にユリ、モエレ沼公園にはサクラ、そして平岡公園にはウメを植栽する方針を立て、それぞれ造成したそうです。
それが今では見事な梅林に成長し、開花期間中は毎年、10~16万人の来園者があるそうです。
ただし、北海道は梅の北限を越えているそうで、毎年、きれいな花を咲かせるために、平岡公園職員たちは結構、苦労しているようです。
梅の歴史にはいろいろな説があるそうですが、中国から日本に渡来してきた植物というのが定説だそうです。遣唐使が持ち帰ったのが始まりとされています。
 新元号「令和」は、奈良時代に編集された万葉集の「梅花の歌」から採用されたといいます。この日、ガイドしてくれた公園職員によると、「奈良時代はまだ白梅しかなかったので、おそらく白梅を見て詠まれた歌でしょう」と話していました。
新元号「令和」は、奈良時代に編集された万葉集の「梅花の歌」から採用されたといいます。この日、ガイドしてくれた公園職員によると、「奈良時代はまだ白梅しかなかったので、おそらく白梅を見て詠まれた歌でしょう」と話していました。
ちなみに、平安時代には天皇の病気治療に梅干しが利用されたそうですが、庶民が梅の実を口にできるようになったのは江戸時代になってからだといいます。それまでは高貴な一部の人のための物だったようです。
「梅干し弁当」は意外にも高貴な食べ物だったのかもしれませんね。
なお、今年の平岡公園のウメの見ごろは5月5日~8日ごろだそうです。
[広告]