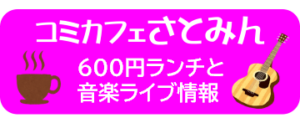苫小牧市のウトナイ湖サンクチュアリ自然観察路を歩いてきました(2021年8月13日)。湖畔や湿原、森林の中を行く自然観察路。この時期、野鳥はあまり見かけませんでしたが、自然を満喫しながらさわやかな散策が楽しめました。
 国道36号線に面した「道の駅ウトナイ湖」は以前から、車でここを通るたびによく利用してきました。ちょっと湖畔に出ることもでき、ここでもウトナイ湖の自然を感じることが出来ます。
国道36号線に面した「道の駅ウトナイ湖」は以前から、車でここを通るたびによく利用してきました。ちょっと湖畔に出ることもでき、ここでもウトナイ湖の自然を感じることが出来ます。
でも、道の駅隣の環境省「ウトナイ湖野生鳥獣保護センター」を起点にしたウトナイ湖自然観察路を歩くと、もっとウトナイ湖の自然を満喫できそうです。早速、自然観察路を歩いてみました。

自然観察路マップ

湖のほとりを歩く所も
ウッドチップの道を進むと、まもなく湖畔に出ます。あずまややウッドテラスなどがあって、ウトナイ湖を眺めたり、野鳥を観察したりできるようになっているようです。
春夏は渡り鳥でにぎわうそうですが、この時期はあまり見かけません。道端にホザキシモツケなどの野の花が咲いていました。ここは、野鳥だけでなく野の花の天国でもあるようです。

ホザキシモツケ

オニユリ

湿地帯には木道が伸びる
ちなみにウトナイ湖は、270種もの野鳥が確認されているそうです。周囲9㎞、平均水深0.6m(意外に浅い!)。国指定鳥獣保護区で、ラムサール条約の登録湿地でもあります。

オタルマップ川を渡る
さらに進むと、湖畔から森の中に入ります。途中、ウトナイ湖に注ぐオタルマップ川という小川があり、木道の橋を渡ります。
この辺りは、湿地帯になっていて、道は木道になっています。

マガンのテラス
しばらく歩くと再び湖畔に出ます。「マガンのテラス」「ハクチョウのデッキ」など名前がついた眺望施設があります。

かつてウトナイ湖ユースホステルがあった場所。再び森に還ろうとしている
途中、「ウッドネットの森」という看板が立つ場所がありました。「ユースホステル跡地緑化事業」で白樺などの樹木が植栽されていました。
調べてみると、ここにはかつてウトナイ湖ユースホステルがあったそうです。2005年閉館し、2006年建物は解体されました。45年間ほど営業したそうです。

ネイチャーセンター
きっと、多くの若者や旅人でにぎわった頃もあったのでしょう。今は再び森に還ろうとしています。

タスオ池
ここから再び森の中の道に入り、間もなくして日本野鳥の会の「ネイチャーセンター」に到着しました。ウトナイ湖の観察や学習ができる施設ですが、開館は土日と祝日だけで、この日は残念ながら閉館していました。
さらに、森の中の道を奥に歩いて行きました。キタキツネの小径と名付けられた道脇に、水たまりのような池がありました。「タスオ池」というそうです。
エゾリスや野鳥などの水飲み場、水浴び場になっている池だそうです。干上がっていることも多いということですが、ちゃんと水は入っていました。
この「タスオ池」は自然の水たまりではなく、人工の水たまりです。なんでも池を掘ったのが「タザワさん、スガタさん、オダさん」の3人で、その頭文字をとって、「タスオ池」となったそうですよ。

草原の観察小屋
やがて自然観察路の一番奥、「草原の観察小屋」に到着です。野の花の観察などをしながら歩いてきて、ここまで1時間ほどたったでしょうか。小屋の中に入ってみると、野鳥観察ができるような仕掛けになっていました。
ここからは「シマアオジの小径」と名づけられた森の中の道を湖畔に向かって歩きます。
ウトナイ湖自然観察路は湖畔、ヨシ原、湿原、森林と環境が変わるのを感じながら散策できるのが特徴なのでしょう。

イソシギのテラス
再び湖畔に出ました。「イソシギのテラス」というのがあって、ウトナイ湖とヨシ原が広がっています。ここからヨシ原の湖畔沿いをしばらく歩くと「湖岸の観察小屋」に着きました。
ただし、イソシギのテラスから湖岸の観察小屋までの道(イソシギの小径)は細い踏み分け道で、数日前の雨で冠水し、とても歩きづらかったです。雪解けの頃も冠水するようです。

エゾミソハギ

トモエソウ

ウトナイ湖野生鳥獣保護センター
ここ「湖岸の観察小屋」から、また出発点の野生鳥獣保護センターまで歩いて戻りました。全行程2時間超の散策でした。
自然観察路の道端で、さまざまな野の花を見かけました。エゾミソハギ、ツリフネソウ、ホザキシモツケ、オニユリ、トモエソウ、サワギキョウほか。サワギキョウは毒草だそうです。名前の分からない花も多くありました。

サワギキョウ

ツリフネソウ
ウトナイ湖は素晴らしい自然の宝庫で、それを身近に感じられる場所です。多くの人の努力で、この自然が保たれているのを強く感じました。
[広告]