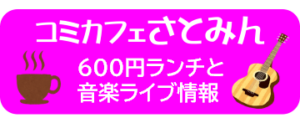あしりべつ郷土館(札幌市清田区清田1条2丁目、清田区民センター2階)は9月6日(火)、平岡公園小学校(清田区平岡公園東5丁目)の3年生児童にオンライン授業を行いました。

あしりべつ郷土館からオンライン授業
平岡公園小学校の郷土史学習について、児童たちに郷土館に来てもらうか、郷土館スタッフが平岡公園小に出向いて出前授業する予定でしたが、コロナの感染拡大防止のため、急きょオンライン授業を行うことにしました。

送られてきた映像を大型テレビで見て学習する児童たち
あしりべつ郷土館の館内で、郷土館スタッフの了寛紀明さん(郷土史家、元小学校長)と田山修三さん(北海道文化財保護協会副理事長、元小学校長)の2人がビデオカメラに向かって、館内に展示している農機具や生活道具などを説明し、昔の人たちの暮らしを分かりやすく説明しました。

自前のカメラ機材を持ち込み、撮影する園部さん
カメラ撮影は映像業務に詳しい郷土館スタッフの園部真人さん(元小学校長)が担当。同じくスタッフの水野重男さん(清田区ITボランティア、パソコン教室講師)がオンラインの操作を担当し、生放送で映像と音声を平岡公園小に送りました。
写真撮影と記録は川島亨さん(地域メディア「ひろまある清田」)が担当しました。あしりべつ郷土館と平岡公園小学校の両方の会場を行ったり来たりしましたので、学校での子供たちの様子もしっかり記録することができました。
平岡公園小では、3年生4クラスがそれぞれの教室で大型テレビの映像を見入り、あしりべつ郷土館と清田区の昔の人たちの暮らしを学びました。

昔の農機具を説明する了寛さん
了寛さんと田山さんは、館内に展示しているクワや脱穀機などの農機具やランプ、炭アイロンなど昔の生活道具などを手に取り、オンラインで子供たちに語り掛けるように説明しました。

昔の暮らしを説明する田山さん
また、「清田区は昔、アシリベツと呼ばれていました。これは〇〇を捕る仕掛けの多い川という意味ですが、さて何を捕る仕掛けでしょう」といったクイズを出し、子供たちと双方向でやり取りしました。ちなみに、この答えはサケです。
最後に、質疑応答もオンラインで行いました。「昔の人はどんな動物を獲っていたのですか」「消防団はどんな仕事をしていたのですか」など次々と児童たちから質問があり、了寛さんと田山さんが一つ一つ丁寧に答えていました。

オンライン授業に取り組んだ「あしりべつ郷土館」ボランティアスタッフ
郷土館ボランティアスタッフのみで取り組んだ初のオンライン授業は、コロナ禍の中でのやむを得ぬ事情で行った取り組みですが、平岡公園小学校の先生たちの協力もあり、無事終了しました。子供たちも喜んでくれて、郷土館としても貴重な体験となりました。
[広告]