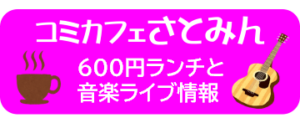厚別川(あしりべつ川)に架かる橋のたもとには、北海道による「川名」と「川名の由来」を書いた看板が立っています。この看板の表記は正しいのでしょうか。地元の郷土史研究家から疑問の声が上がっています。これは川の名の由来だけでなく、昔の清田の地名「あしりべつ」の由来にも関わることです。

この看板表記は正しいのでしょうか。かねてから疑問の声が出ています
厚別川の看板には次のように「川の名の由来」が記されています。
『アイヌ語の「アッ・ペッ:オヒョウのある川」が由来だといわれています。
また、「ハシ・ペッ:低木の中を流れる川」という説もあります。』
この説明書きに疑問を呈しているのは、清田区の郷土史研究家の了寛紀明氏(元清田小学校校長)です。

清田区のシンボル、厚別(あしりべつ)川
了寛氏は江戸時代から明治にかけての膨大な絵図、記録、地図、新聞などの古史料を採取して調べ上げ、厚別川および流域の地名が当時、どう呼ばれていたのか、どう表記されていたのか、綿密に調査しました。
それによると、この川および川の流域は、「アシユシヘツ」「アシシベツ」「アツシヘツ」「ハシスベツ」など似た表記が数十種もあることが分かりました。アイヌ語の発音は微妙で、日本語のカタカナ表記にすると、様々な表記になってしまったようです。
様々な表記・呼び方がある中で、「アシリベツというのが発音がしやすかったのと、聞いてる側にとっても明確に理解できたことによって、明治になってアシリベツという表記・読み方が地域に根付いていったものと考える」と了寛氏は言っています。
さらに、明治10年代以降、この「アシリベツ」の漢字表記には、開拓使が用いた「厚別」が当てられ一般化していきました。しかし、読み方は「あしりべつ」でした。
「厚別」を「あつべつ」と一般に呼ぶようになったのは、明治27年、鉄道(現函館本線)の「厚別駅」ができたころからといいます。厚別駅は最初から「あつべつ」駅と呼びました。
このため、厚別川下流域(今の厚別区)では「あつべつ」という呼称が一般化し、厚別川も「あつべつがわ」と呼称するようになったといいます。しかし、厚別川上流域(今の清田区)では、種々の発音が「あしりべつ」に統一され、厚別川は「あしりべつ川」と呼び、地域名は厚別と書いて「あしりべつ」といいました(昭和19年まで)。今の清田区の地域です。
厚別川は厚別区では「あつべつ川」ですが、清田区では今も「あしりべつ川」と呼ばれています。ちなみに厚別神社は「あしりべつ神社」と言います。清田小学校、清田中学校は昭和47年まで「厚別(あしりべつ)小学校」「厚別(あしりべつ)中学校」という校名でした。
さて、厚別川の看板に戻りましょう。
「アイヌ語のアッ・ペッ=オヒョウのある川が由来だ」との語源説明は疑問だと了寛紀明氏は言います。「アッ・ペッ」は「アシリベツ」の漢字表記「厚別」から来たものであり、由来説明になっていないというのが了寛氏の指摘です。
この「アッ・ペッ」説は、昭和29年「北海道駅名の起源」(高倉新一郎、知里真志保、更科源蔵、河野広道)から生じているようです。この著作では厚別駅の起源は「アイヌ語『アツ・ペッ』(オヒョウダモのある川)から出たのである」とあります。
了寛氏は「高名な先生方の著作は強力な説になっていった。しかし、アッ・ペッは何を基にしたのだろうか」と疑問を呈しています。その後、「厚別」の語源については、この著作を参考にしたと思われるものが数多い、と了寛氏は指摘しているのです。ちなみに、オヒョウ(オヒョウダモ)とはアイヌの服を織る繊維を採る木だそうです。
 アシリベツの地名と川名がでてくる江戸時代から明治にかけての古文書多数を丹念に実証的に調べ上げた了寛氏が最も妥当と判断している説は、松浦武四郎の「戊午東西蝦夷山川地理取調日誌」(安政5年)の記述です。この中で松浦武四郎はアシリベツ川を「アシユウシベツ」と表記し、語源を「樹枝をもってウラエを架したことから名づけられた」と説明。さらに、「アシユシとは木の枝のこと」と注釈もつけています。
アシリベツの地名と川名がでてくる江戸時代から明治にかけての古文書多数を丹念に実証的に調べ上げた了寛氏が最も妥当と判断している説は、松浦武四郎の「戊午東西蝦夷山川地理取調日誌」(安政5年)の記述です。この中で松浦武四郎はアシリベツ川を「アシユウシベツ」と表記し、語源を「樹枝をもってウラエを架したことから名づけられた」と説明。さらに、「アシユシとは木の枝のこと」と注釈もつけています。
ウラエ(ウライ)とは、サケを捕獲するために川の中に木の杭を打ち込み、柵上にしてサケの通り道をふさぎ、川岸や捕獲場にサケを誘い込む手法のことです。アシリベツ川の語源は「ウラエ(簗場)のある川」というわけです。
明治になって白野夏雲(札幌史学会員)の「蝦夷地名考」という著作が発刊され、松浦武四郎と同様の説を述べています。
松浦武四郎、白野夏雲両氏とも発音と語源から説き起こしており、了寛氏は「この両氏の説明を否定できないどころか重要視するべきである」としています。
なお、厚別川の看板では、川の呼び方に「あつべつがわ」とルビをふっています。行政としてはこの読みで統一しているのでしょうが、「清田区内では『あしりべつがわ』と呼ばれています」という表記があってもいいのではないでしょうか。そうしないと、川の名の由来も説明できません。川の名が上流と下流で違っていることはほかにも例があることです。
さて、厚別川の看板に書いてあるもう一つの説「ハシ・ペッ」(低木の中を流れる川)について。これは、本来の発音から来ている解釈であり、了寛氏も「アッ・ペッ」ほど否定的ではありません。しかし、「いくつもの資料を基にした確実な表記にしておかなければ、誤記がまた広がっていくことを懸念するばかりである」と憂慮しています。
こうした了寛紀明氏の指摘について、河川を管理する北海道空知総合振興局札幌建設管理部事業課にお尋ねしましたが、明確な回答や説明は得られませんでした。

旧道に架かる橋の名は「あしりべつはし」となっています
あしりべつは清田区の昔の地名です。区内では、誇りを持ってこの「あしりべつ」という表記を大事にしようという空気があります。この由来の説明がいい加減であってはならないと思います。

了寛紀明氏の著作「札幌本道と厚別地域の歴史」
行政の看板が間違った表記をしていたら、そのうち間違いが独り歩きして定着してしまいます。少なくとも、行政としてはあやふやなことは記載しない方がいいのではないでしょうか。
あしりべつの語源と厚別川の看板表記への疑問については、了寛紀明氏の著作「札幌本道と厚別(あしりべつ)地域の歴史」-古文書を辿っての「清田発掘」-(2018年)に詳しく記載されています。この書物は清田図書館にあり、どなたでも読むことができます。
[広告]