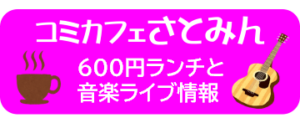札幌市手稲区の山口運河は、明治の開拓期に造られた舟運の運河水路の名残です。今では一部が往時をしのぶ姿に整備され、さらに水路わきに樹林に囲まれた散策路も造成されて、格好の散策・ウオーキングスポットになっています。
 山口運河は、手稲区の星置と手稲山口の境を西から東に、ほぼまっすぐ流れる水路で、長さは1.6キロ。水路沿いに散策路があります。
山口運河は、手稲区の星置と手稲山口の境を西から東に、ほぼまっすぐ流れる水路で、長さは1.6キロ。水路沿いに散策路があります。
西端の星野通から山口運河に入り、東方向に歩きだします。山口運河は3つのゾーンに区分けされており、星野通から星置2号橋までの500メートルは「山口運河ゾーン」、その先、星置駅前通に架かる星運橋までの500メートルは「ふれあいゾーン」、さらにその先、濁川と交わる所までの600メートルは「樹林の散策ゾーン」というそうです。
運河ゾーンは、水路の底や側壁が石で固められ人工的な趣を見せ、あずま屋も整備されています。赤さびのような土がたまるようで、水は赤く濁った感じです。
 ふれあいゾーンは親水公園のような趣で、実際、散策していると、カモたちと出会いました。
ふれあいゾーンは親水公園のような趣で、実際、散策していると、カモたちと出会いました。

散策路からカボチャ畑が見えました
樹林ゾーンは、樹木に覆われた緑道が600メートル続きます。そばの水路は、細い流れになります。散策路の外を見ると、カボチャ畑なども目に飛び込んできました。札幌でもこの辺はまだ田園風景もあります。

散策路の中のベンチで休憩
散策路が整備されているのは、濁川との交点の山口運河橋までですが、地図を見ると、水路はその先も「手稲排水川」として遠く新川まで続きます。

樹林ゾーンの山口運河は自然の川のような趣
山口運河橋でUターンして、往復すると、3.2キロの散策・ウオーキングになります。実際、散策やウオーキング、犬の散歩をする人たちと出会いました。
 歴史をひも解くと、山口運河は明治30年(1897年)に完成した「花畔・銭函間運河」の一部だそうです。幅は4.1メートル、水深は60センチだったそうです。当時、小樽から米や味噌、醤油、酒などの生活物資を積んで小舟で札幌まで運んだ運河であり、また山口地区の農業用水にも使ったようです。一日、20艘ほどの小舟が行き来したといいます。
歴史をひも解くと、山口運河は明治30年(1897年)に完成した「花畔・銭函間運河」の一部だそうです。幅は4.1メートル、水深は60センチだったそうです。当時、小樽から米や味噌、醤油、酒などの生活物資を積んで小舟で札幌まで運んだ運河であり、また山口地区の農業用水にも使ったようです。一日、20艘ほどの小舟が行き来したといいます。
しかし、まもなく道路が整い鉄道が敷かれ、運河は7年ほどで役割を終えてしまいました。
再び脚光を浴びるようになったのは、平成元年(1989年)の手稲区誕生からです。同年から10年ほどかけて札幌市が運河の護岸や散策路を整備しました。

山口運河の水源はポンプでくみ上げた地下水
山口運河は星置通脇の小さな湧き水から始まっているように見えますが、1960年代の治水事業で水源の星置川から分断されたため、今は地下水をポンプでくみ上げているそうです。
今では毎年9月に地元の連合町内会などが「手稲山口運河まつり」を開催し、2019年までに23回を数えました。歴史遺産が地域をつなぐシンボルになっているんですね。山口運河を会場に、往時の物資運搬の運上船の再現などが人気ですが、2020年はコロナのために中止です。
山口運河のある手稲山口は、明治15年(1882年)、この地に最初に入植したのが山口県人だったことから「山口」と命名されたそうです。
山口運河と緑の樹林は、札幌の歴史ロマンが感じられる散策路です。
[広告]