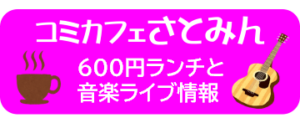2018年9月6日の北海道胆振東部地震では、札幌市清田区の清田団地(清田中央地区)で、地割れや地盤沈下等の宅地崩壊が起きました。しかも、この地区は1968年(昭和43年)の十勝沖地震、1982年の浦河沖地震、2003年の十勝沖地震でも被害が起きたといい、なんと過去50年間に4度も地震被害が発生したことになります。ちょっと多すぎませんか。

清田中央地区
何か根本的な対策が必要と思われますが、清田区里塚や美しが丘のような地盤補強や液状化防止等の対策工事の動きはありません。
2018年の地震後に現地に入った研究者ら専門家の調査報告(複数)によると、清田中央地区で、地震のたびに住宅や宅地、道路の被害が発生しているのは清田7条2丁目と同3丁目、清田6条3丁目界隈と指摘されています。
2018年の北海道胆振東部地震では、この界隈は地盤沈下や住宅の傾き、地割れ、地表面のずれなど様々な地形変状の被害が発生しました。
この地区で最初の地震被害は1968年(昭和43年)5月16日の十勝沖地震(札幌震度4)の時です。「清田団地のあゆみ」(1975年発行)によると、当時の清田団地の総戸数320戸のうち、56戸の家屋が倒壊、傾斜、破損したといいます。また、下水管の破裂、地下湧水の吹き出しで泥水につかる家屋が120戸に達したといいます。水道管も、地割れ・陥没により破損し、断水しました。
当時の町内会長は「河川用地や沢地を埋め立てた軟弱地であるため被害が集中した」と、「清田団地のあゆみ」の中で記しています。

1968年、2003年、2018年の地震で被害が発生した箇所(地盤工学会・土木学会「北海道胆振東部地震による液状化被害」(インターネット上で公開)=2018年9月21日、右下が北方向、左上が南方向。図上方の大きな白地部分は清田南公園)
この地区では、その後も2003年の十勝沖地震(札幌震度4)、そして2年前の2018年の北海道胆振東部地震(清田区震度5強)でも、地盤変状、宅地崩壊、家の傾斜、地割れ等の被害が発生しています。

2018年の地震でできた地割れ。2003年にもほぼ同じ場所と向きで地割れが発生した
2003年と2018年の地震では、ほぼ同じ位置に少し長い地割れが起きたことも判明しています(清田7条2丁目、3丁目)。専門家によると、この地割れは「地山と谷底の境界付近に沿って発生している。このことから、切り盛り境界に沿って盛り土が滑動した可能性がある」(後述の「平成30年北海道胆振東部地震による札幌市清田区美しが丘・清田における地震災害」)と分析しています。
研究者によっては、1982年の浦河沖地震でも被害が出たといい、それを含めると50年間で4度もこの地区では地震による被災が繰り返し発生していることになります。過去4回の地震では、概ねこの地区のどこかで必ず被害が出たというのです。
この地区では、なぜ地震のたびに被害を出すのでしょうか。
2018年の地震直後に清田に調査に入った京都大学防災研究所教授の釜井俊孝教授は「宅地崩壊」(NHK出版新書)の中で、「地質と宅地の造成方法に原因がある」と指摘しています。
つまり、この地区は造成前、幾筋もの深い谷が刻まれていましたが、平らな宅地を造るために尾根を崩して谷を埋める作業を繰り返しました。谷埋め盛り土の材料は、この地を覆う支笏火山の火山灰と軽石でした。そこに地下水が集まり、水位が上がると液状化が発生しやすくなると、釜井教授は指摘しているのです。清田も里塚と同じ構図です。
さらに、インターネット上に公開されている専門家のレポート「平成30年北海道胆振東部地震による札幌市清田区美しが丘・清田における地震災害」(若松加寿江関東学院大学研究員、尾上篤生長岡高専名誉教授、2018年9月24日)は次のように指摘しています。
「清田で繰り返し被害が発生する場所は、2本の谷(小川)が合流する地区である。このことは、造成によって地形が変わっても、旧谷筋には依然として地下水が流れており、雨水も集めていることを示唆していると考えられる」
では、この地区の宅地造成前の旧地形がどうだったのか、見てみましょう。

札幌市大規模盛土造成地マップ。清田南公園の上方で、同公園の左右から二つの大きな盛り土造成地(濃い緑と薄い緑の部分)が合流している。この付近を中心に地震被害が繰り返し発生
札幌市が作成・公表した「札幌市大規模盛土造成地マップ」によると、清田7条2丁目と3丁目の境付近(コンビニ前付近)で、二つの大きな盛り土が合流しているのが分かります。この盛り土地帯は、かつては川が流れていたと思われます。
そこで、国土地理院が2018年9月の地震後に作成・公表した「札幌市清田区の地形復元図」を見てみましょう。これは清田区の宅地造成前の地形がどうだったのかを示す地形図です。

清田区地形復元図(国土地理院)。真ん中の水色部分は清田川の谷底平野。その周辺のピンク色部分は台地縁辺の崖。青色の点線は凹地の谷線(沢、川)。清田川には幾筋もの谷(小川)が合流していたのが分かる。図下方の薄緑色の大きな四角は清田南公園
これによると、今の清田南公園から流れてくる清田川(水色部分)を中心に、清田7条2丁目、3丁目の境付近で支流(谷、青い点線で表示)が合流しているのが分かります。他にも幾筋かの谷筋が清田川に合流しているのが分かります。
清田川は現在、清田南公園から清田南小学校前までは暗渠になって、商店などが点在する清田中央地区のメーンストリートの地下を流れています。
この暗渠の清田川と、それに合流する谷筋付近の盛土を中心に、地震被害が多発していると指摘されています。川や谷は埋め立てられ、かつて川や谷がどこにあったのか、現在は分かりにくくなっています。
清田団地の開発造成は早くから行われ、昭和34年(1959年)頃から始まったといいます。2018年の地震では、里塚地区のような極端で特異な地盤崩壊や家の傾きはなかったものの50年間に3回ないし4回もの地盤崩壊は異常です。
こんなに何度も被害を繰り返すのは、札幌市内でもここだけです。なお、美しが丘地区では2003年と2018年の地震で2回、液状化被害が発生しています。
里塚や美しが丘地区では、札幌市による地盤補強や液状化防止等の対策工事が進められていますが、清田中央地区では何も行われていません。このまま何も対策しなくて大丈夫なのでしょうか。
[広告]