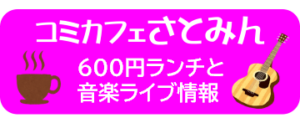今回の地震で宅地や道路が大きく陥没し、多くの家が傾いた清田区里塚1条1丁目、2丁目地区。専門家は、その原因について「大きな揺れによって、水分の多い地盤が液状化して地下で地滑りが発生し、さらに破損した水道管から大量の水が流れ出て土砂が道路上にあふれた」(9月9日北海道新聞)といった分析をしています。

北海道開拓使「新道出来形絵図」の三里塚付近
 陥没が起こった地域は、約2ヘクタールに及び、地元の人は「昔は川が流れて沢があった。そこを埋め立てて、昭和50年代前半に宅地造成された」といいます。
陥没が起こった地域は、約2ヘクタールに及び、地元の人は「昔は川が流れて沢があった。そこを埋め立てて、昭和50年代前半に宅地造成された」といいます。
この地域は一体どんな地形だったのでしょうか。
その手掛かりとなる古い資料があります。
明治6年(1873年)、北海道開拓使が「新道出来形絵図」という北海道最初と思われる道路地図をつくり、そこに当時の三里塚の様子と地形、川の流れが記載されています。
この絵図は、開拓使が、今の国道36号線の基になった札幌本道(札幌ー函館)を開削した際につくったものです。札幌本道は開拓顧問のケプロンの指摘で建設を決め、開拓次官の黒田清隆が陣頭指揮をとったといいます。「新道出来形絵図」は49枚組の彩色絵で、明治初期の北海道の様子を伝える貴重な史料です。
上記の「新道出来形絵図」の写真をご覧ください。今回の地震被害地区付近の絵図です。
左下(札幌中心部方面)から右上(千歳方面)に描かれているのが札幌本道、今の旧道(旧国道36号線)です。そして、右の上流方向から左の下流方向に川が流れているのが描かれています。川は橋の下を通り、下流方向に流れて行っているように見えます。
谷を流れる川には、幾重にも木のやぐらが組まれ、その上に札幌本道の木橋が架けられています。この谷は相当深く大きいように見えます。
 この絵に描かれている川は、現在は暗渠(地下に設けた水路)になっており、谷は土砂で埋められて宅地になり、住宅が立ち並ぶようになりました。そして、ここで今回の陥没、液状化が起きたのです。
この絵に描かれている川は、現在は暗渠(地下に設けた水路)になっており、谷は土砂で埋められて宅地になり、住宅が立ち並ぶようになりました。そして、ここで今回の陥没、液状化が起きたのです。
現地を歩くと、陥没、沈下、建物の傾き、液状化は、この絵図に描かれた川の水の流れとほぼ一致するように線上に連なって起きたように見えます。
橋を支える木のやぐらは相当大がかりなものに見えます。それだけ川の谷が大きく深かったと思われます。現在は、川も谷筋も埋めてしまったので、明治初期のもともとの地形は想像すらできないほど変わってしまっています。
かつての川と谷筋沿いに起きた陥没、沈下、液状化。人工的に地形を変えても、自然の力を完全に抑えるのはやはり無理なのか、そんな思いが頭をよぎります。

旧道下の暗渠の出口。三里川はここから表に出て平岡公園方面に流れていく
川は、旧道の「桂台団地」バス停付近の下を通って、ようやく地表に出て、小さな水路になって平岡公園に流れていきます。これが三里川です。旧道の下を通った所に暗渠の出口があります。

旧道から下流は地表に出て平岡公園方面に流れていく三里川
「桂台団地」バス停付近の旧道は地震後、液状化で噴出した土砂で埋まり、一日中、通行止めになった所です。
旧道から上流方向は地下にもぐってしまうので、川がどこをどう流れてきているのか、今ではわからない状態です。今回の地震被害の発生状況から、昔の川筋が見えてきた、という人もいます。
「新道出来形絵図」を見ると、三里川の橋のたもとに木柱が立っているのが見えます。これは札幌中心部から3里の距離を示す里程標で、北海道開拓使が建てたものです。三里塚の里程標が建てられたことで、この川は三里川と呼ばれるようになり、この地域を「三里塚」(さんりづか)と呼ぶようになりました。
その後、昭和19年に「三」をとって「里塚」(さとづか)という地名になりました。しかし、今でも三里塚小学校、三里塚神社、三里塚公園など三里塚の名称は一部で残っています。
「新道出来形絵図」は明治初期の史料なので、必ずしも正確ではないかもしれませんが、今回の清田区里塚の特異な地震被害を解明する一つの手がかりにはなるように思います。
[広告]