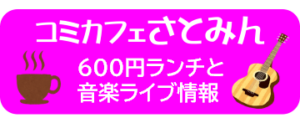清田区は昔、アシリベツという地名でした。「厚別」と書いて「あしりべつ」と読みました。あしりべつの歴史の最初の頃を調べてみると、「明治2年(1869年)、木村という人が今の真栄で駅逓を営む」とあります。清田区の始まりは、この駅逓から始まったのかもしれません。

旧簾舞通行屋(札幌市南区簾舞)。このような通行屋が清田にもあった!

通行屋内部
駅逓とは旅館や休憩所のような施設で、当時、江戸末期に開削された札幌越新道という細い道があり、そこを行き来する人たちの休憩所だったようです。今の真栄小学校付近にあったといいます。

通行屋客室
さらに、明治6年(1873年)に札幌本道(室蘭街道)=国道36号線のもと=ができると、「中西安蔵という人が清田小学校のところで駅逓を始めた」とあります。清田地域の最初の開拓者・長岡重治翁が入植したのもこの年です。この駅逓は明治11年、長岡重治の子、徳太郎が中西安蔵から引き継いだといいます。
通行屋や駅逓は明治の初め、札幌にいくつか誕生しましたが、清田をはじめほとんどが現存せず、残っているのは旧簾舞通行屋と北広島市島松の旧駅逓の2つだけだそうです。
明治の初めに清田にあったという駅逓(通行屋)の面影を求めて、旧簾舞通行屋(札幌市南区簾舞1条2丁目)を訪ねました。

郷土資料館の展示
旧簾舞通行屋は、札幌から定山渓を経て有珠に至る道が明治4年(1871年)に開通したことに伴い、要所となる簾舞に明治5年に建てられました。明治6年に札幌本道ができると、次第に簾舞を通行する者が減り、明治17年に廃止となりました。
その後、通行屋守だった黒岩家の住宅として代々使われてきましたが、人が住まなくなった後の昭和59年、札幌市の有形文化財に指定されました。
 そして昭和61年、簾舞郷土資料館として一般公開され、今日に至っています。中は、炉付きの広間と4つの部屋で構成する宿泊機能を考慮したつくりになっており、馬小屋や納屋などもあります。当時の雰囲気を今に伝えるつくりで、清田小学校のところにあった通行屋も、きっとこのような感じだったのか、と思いめぐらしたりします。
そして昭和61年、簾舞郷土資料館として一般公開され、今日に至っています。中は、炉付きの広間と4つの部屋で構成する宿泊機能を考慮したつくりになっており、馬小屋や納屋などもあります。当時の雰囲気を今に伝えるつくりで、清田小学校のところにあった通行屋も、きっとこのような感じだったのか、と思いめぐらしたりします。
簾舞地区の開拓者や農家が使った農機具や生活用具などの展示もあります。
■所在地 札幌市南区簾舞1条2丁目
■電話 011-596-2825
■休館日 月曜日(祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日、年末年始
■観覧時間 9時~16時
■入館無料
■交通手段 地下鉄真駒内駅より定山渓方面行き乗車
・定鉄バス「国立札幌南病院前」下車 徒歩2分
・定鉄バス「東簾舞」下車 徒歩5分
[広告]