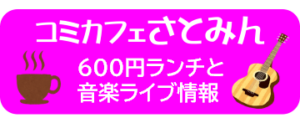災害時に役立つ風呂敷の活用方法を学ぶ「防災風呂敷講座」が2月8日(金)、里塚児童会館(札幌市清田区里塚2条3丁目)で開催されました。

出来上がった風呂敷帽子をかぶり、風呂敷リュックを背負う参加者
 日本風呂敷協会・認定講師・北海道代表の横山芳江さんが、昨年の北海道胆振東部地震で大きな被害が発生した里塚で開催しました。
日本風呂敷協会・認定講師・北海道代表の横山芳江さんが、昨年の北海道胆振東部地震で大きな被害が発生した里塚で開催しました。

便利な袋になります
日本の伝統的な生活用品である風呂敷は、様々なバッグの出現であまり使われなくなっていましたが、近年、繰り返し使えて環境にやさしいイメージと、粋な雰囲気もあって、見直されているようです。

こんな利用法もあります
清田区内でも、清田区民センターで「粋な大人の風呂敷活用術」などの講座が開催され、人気となっています。
風呂敷は、災害時のいざというときにも様々な活用がある優れもののようです。その活用術を伝授したのが、今回、里塚児童会館で行われた「防災風呂敷講座」です。

頭部を守る風呂敷頭巾。火事の時は水にぬらして使います
参加者は、講師の横山さんの指導で、「真結び」と「ひとつ結び」の基本から学びました。基本を終えると、早速、風呂敷とスーパー・コンビニのビニール袋を使った災害時の給水袋をつくりました。ビニール袋だけだと破れやすいですが、風呂敷の活用でぐんと強度が増すようです。

足袋にもなります
ほかにも、赤ちゃんを抱っこする袋や、けが人の応急手当てに役立つ風呂敷三角巾、頭部を守る風呂敷頭巾、風呂敷2枚を使ってつくるリュックサック、風呂敷でつくる足袋など様々な活用術を学びました。
風呂敷は、災害時にも大いに役立つ生活ツールなんですね。参加者は改めて風呂敷のすごさを認識した様子でした。
[広告]